記事一覧
1 - 5件目まで(6件中)

- ミラノ大聖堂にて六本木合唱団のレクイエム
-
エリア:
- ヨーロッパ>イタリア>ミラノ
- テーマ:お祭り・イベント 鑑賞・観戦
- 投稿日:2010/11/28 00:41
- コメント(1)
ミラノ滞在たった一泊のその夜に、大聖堂で日本人の演奏会がある事を当日の朝に知った。
大聖堂へ行くとポスターが貼ってあり、錚々たるメンバーである。
 三枝成彰『レクイエム』曽野綾子のリブレット
三枝成彰『レクイエム』曽野綾子のリブレット
指揮:大友直人 ソプラノ:中丸三千繪 テノール:樋口達哉 オーケストラ:日本フィルハーモニック アンサンブル管弦楽団
チャリティーコンサートであり、シンガーもオーケストラも基本的に自費で参加しているのだそうだ。しかも、入場料まで無料。これを千載一遇の機会というのだろう。行ってみることにする。
20時半開演とのこと。
19時から近くで簡単に食事を済ませて、20時には大聖堂前で開場を待とうと…
 おお、すでに長い行列が、美しくライトアップしたミラノ大聖堂の前に出来ている。
おお、すでに長い行列が、美しくライトアップしたミラノ大聖堂の前に出来ている。
行列のうしろの方で並んでいると、突然大聖堂のもうひとつの扉が開く事になり、走って移動。イタリアらしい(笑)おかげでそこそこの席を確保できた。

大聖堂、あまりに残響時間の長い空間なので、音がどんな風に聞こえてくるのか少々不安を感じながら待つ。
時間となり、イタリア語で作曲の三枝成彰、作詞の曾野綾子、両氏も紹介があった。わざわざ日本から臨席されていたのである。
その後、日本語の上手なイタリア人神父が話はじめる。
「昨年ミラノの大司教が日本を訪問し、六本木合唱団の歌声を聞く機会があり、とても感激されました。『ミラノの大聖堂で歌いませんか』と申し出があり、今日が実現したのです」
「レクイエムは、苦しみの中で亡くなった人々を思う曲です。皆さんもご先祖様を思ってお聞き下さい」
静かで重々しく、荘厳にもりあがってゆく楽曲。歌声が大聖堂の中空で交じり合い、まさに大聖堂ならではの音響になってゆく。思ったとおり非常にライブな空間である。
大人数の男性コーラスの音圧はなかなか気持ちが良い。そこを切り込むように紅一点中丸さんの声が彩りになる。
ただ、その残響の長さ故、歌詞はほぼ聞き取れない。せっかく日本語詩なのだが・・・そこはとても残念に思わざるを得ない。席に置かれていたリーフレットにはイタリア語の翻訳だけ載せられていたが、日本語詩も是非ほしかった。
一時間半近くをノンストップで演奏。
未知の曲ゆえ、観客はどこで拍手を送るべきなのか、少々とまどっているように見える。
指揮の大友氏の肩が、ふうっとゆるくなり、前方から拍手が沸きあがってきた。
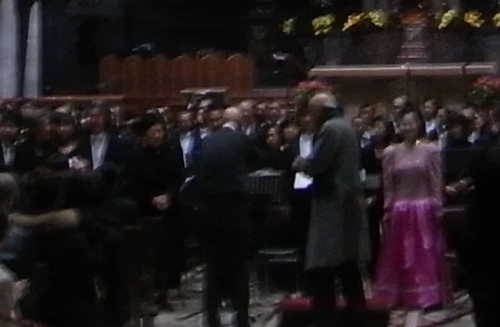
明日11月26日はローマのバチカンでミサ曲を演奏するという事。我々はちょうど日本への飛行機に乗っている時間である。
タイミングよくミラノ大聖堂で日本人の奉納コンサートに出会えた事に感謝しよう。
大聖堂へ行くとポスターが貼ってあり、錚々たるメンバーである。
 三枝成彰『レクイエム』曽野綾子のリブレット
三枝成彰『レクイエム』曽野綾子のリブレット指揮:大友直人 ソプラノ:中丸三千繪 テノール:樋口達哉 オーケストラ:日本フィルハーモニック アンサンブル管弦楽団
チャリティーコンサートであり、シンガーもオーケストラも基本的に自費で参加しているのだそうだ。しかも、入場料まで無料。これを千載一遇の機会というのだろう。行ってみることにする。
20時半開演とのこと。
19時から近くで簡単に食事を済ませて、20時には大聖堂前で開場を待とうと…
 おお、すでに長い行列が、美しくライトアップしたミラノ大聖堂の前に出来ている。
おお、すでに長い行列が、美しくライトアップしたミラノ大聖堂の前に出来ている。行列のうしろの方で並んでいると、突然大聖堂のもうひとつの扉が開く事になり、走って移動。イタリアらしい(笑)おかげでそこそこの席を確保できた。

大聖堂、あまりに残響時間の長い空間なので、音がどんな風に聞こえてくるのか少々不安を感じながら待つ。
時間となり、イタリア語で作曲の三枝成彰、作詞の曾野綾子、両氏も紹介があった。わざわざ日本から臨席されていたのである。
その後、日本語の上手なイタリア人神父が話はじめる。
「昨年ミラノの大司教が日本を訪問し、六本木合唱団の歌声を聞く機会があり、とても感激されました。『ミラノの大聖堂で歌いませんか』と申し出があり、今日が実現したのです」
「レクイエムは、苦しみの中で亡くなった人々を思う曲です。皆さんもご先祖様を思ってお聞き下さい」
静かで重々しく、荘厳にもりあがってゆく楽曲。歌声が大聖堂の中空で交じり合い、まさに大聖堂ならではの音響になってゆく。思ったとおり非常にライブな空間である。
大人数の男性コーラスの音圧はなかなか気持ちが良い。そこを切り込むように紅一点中丸さんの声が彩りになる。
ただ、その残響の長さ故、歌詞はほぼ聞き取れない。せっかく日本語詩なのだが・・・そこはとても残念に思わざるを得ない。席に置かれていたリーフレットにはイタリア語の翻訳だけ載せられていたが、日本語詩も是非ほしかった。
一時間半近くをノンストップで演奏。
未知の曲ゆえ、観客はどこで拍手を送るべきなのか、少々とまどっているように見える。
指揮の大友氏の肩が、ふうっとゆるくなり、前方から拍手が沸きあがってきた。
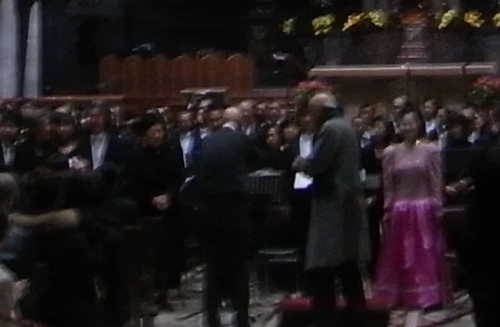
明日11月26日はローマのバチカンでミサ曲を演奏するという事。我々はちょうど日本への飛行機に乗っている時間である。
タイミングよくミラノ大聖堂で日本人の奉納コンサートに出会えた事に感謝しよう。

- ローマにおけるルネッサンスの終焉
-
エリア:
- ヨーロッパ>イタリア>ローマ
- テーマ:歴史・文化・芸術
- 投稿日:2010/11/23 13:08
- コメント(0)
ラファエロが急死して残された未完成の仕事はいちばん弟子のジュリオ・ロマーノが受け継いだ。バチカンの「アテネの学堂」のとなりに位置するコンスタンチヌス帝の間も、生きていればラファエロが別物を描いていただろう場所だ。※写真下

コンスタンチヌス帝が空に現れた十字架を見上げ、「これにて勝て」という啓示をうけている。

ローマ郊外のミルヴィオ橋でマクセンティウスに勝利するコンスタンチヌス。

これら壁に描かれた絵ばかりを見てしまいがちだが、天井にちょっと注目すべき絵がある。キリスト磔刑図の前に粉々になったギリシャの神像が倒れている。

これだけはジュリオ・ロマーノではなく、1585年にトンマーゾ・ラウレティというパレルモ出身の画家によって描かれていた。
見ての通り「キリスト教の異教に対する勝利」を表しているのだが、制作された時代から考えると、これはある種「ローマにおけるルネッサンスの終焉」を象徴しているのだと感じた。
ラファエロは1510年ごろとなりの部屋で「アテネの学堂」を描いた。そこでは学問・芸術・音楽などを象徴してギリシャの神々が美しく描かれている。現在の我々の眼からはもちろん何も違和感ない。
しかし、16世紀はじめにローマを訪れた若きマルチン・ルターにとってはおおいに違った。『キリスト教会の中枢であるバチカン宮殿に堂々とギリシャの神が描かれているとはなんたる事だ!』と憤慨した。
それが後にプロテスタントという分派がうまれる動機のひとつになっていたのだとしたら・・・カソリック教会はやはりルネッサンスを考え直さなくてはならないだろう。
1545年〜63年まで、北イタリアのトレントで断続的にひらかれたカソリック教会の会議において、教会の規律はきびしく引き締められた。粉々になったギリシャ神はまさに、この時期に描かれたものだった。
ラファエロがとなりの部屋に華やかに描いたギリシャ神たちは、壁から削られなかっただけでも幸運だったと言わねばなるまい。

コンスタンチヌス帝が空に現れた十字架を見上げ、「これにて勝て」という啓示をうけている。

ローマ郊外のミルヴィオ橋でマクセンティウスに勝利するコンスタンチヌス。

これら壁に描かれた絵ばかりを見てしまいがちだが、天井にちょっと注目すべき絵がある。キリスト磔刑図の前に粉々になったギリシャの神像が倒れている。

これだけはジュリオ・ロマーノではなく、1585年にトンマーゾ・ラウレティというパレルモ出身の画家によって描かれていた。
見ての通り「キリスト教の異教に対する勝利」を表しているのだが、制作された時代から考えると、これはある種「ローマにおけるルネッサンスの終焉」を象徴しているのだと感じた。
ラファエロは1510年ごろとなりの部屋で「アテネの学堂」を描いた。そこでは学問・芸術・音楽などを象徴してギリシャの神々が美しく描かれている。現在の我々の眼からはもちろん何も違和感ない。
しかし、16世紀はじめにローマを訪れた若きマルチン・ルターにとってはおおいに違った。『キリスト教会の中枢であるバチカン宮殿に堂々とギリシャの神が描かれているとはなんたる事だ!』と憤慨した。
それが後にプロテスタントという分派がうまれる動機のひとつになっていたのだとしたら・・・カソリック教会はやはりルネッサンスを考え直さなくてはならないだろう。
1545年〜63年まで、北イタリアのトレントで断続的にひらかれたカソリック教会の会議において、教会の規律はきびしく引き締められた。粉々になったギリシャ神はまさに、この時期に描かれたものだった。
ラファエロがとなりの部屋に華やかに描いたギリシャ神たちは、壁から削られなかっただけでも幸運だったと言わねばなるまい。
セビリアから一時間もかからない場所にあるカルモナという小さな美しい町。この街のパラドールに泊まるのなら、日暮れ前に是非散歩したい。日暮れ前の一時間の散歩がカルモナの価値であるとさえ思う。
パラドールはこの街の城であった建物。

14世紀半ばのペロド一世王ゆかりといわれる。
入り口はイスラム風のムデハル様式。

パラドールになっているのはごく一部で、背後には巨大な城の廃墟が残されている。
カルモナの表玄関は要塞化されたセビリア門。
傾きかけた太陽の光が赤く染め始めている。

街の中心サン・フェルナンド広場

城壁沿いに歩くと白い壁に夕陽


教会がぽつんとあらわれる

セビリア門と反対側コルドバ門

外は地平線

ローマ時代の城壁にこの門をとりつけ補強した

空の色が蒼く変わりはじめ街頭がぽつり

お気に入りの教会の十字架にはまだカンテラが灯っていなかった…

十分ほど待つとようやく点灯、やはりぽっと暖かくなる


★★★
朝、パラドールのテラスから地平線に朝日がゆっくりのぼってくるのが見える。


朝食の場所は太陽でいっぱいになる

おいしくて食べ過ぎてしまったら…中庭のあるロビーでゆっくりしましょう

パラドールはこの街の城であった建物。

14世紀半ばのペロド一世王ゆかりといわれる。
入り口はイスラム風のムデハル様式。

パラドールになっているのはごく一部で、背後には巨大な城の廃墟が残されている。

カルモナの表玄関は要塞化されたセビリア門。
傾きかけた太陽の光が赤く染め始めている。

街の中心サン・フェルナンド広場

城壁沿いに歩くと白い壁に夕陽


教会がぽつんとあらわれる

セビリア門と反対側コルドバ門

外は地平線

ローマ時代の城壁にこの門をとりつけ補強した

空の色が蒼く変わりはじめ街頭がぽつり

お気に入りの教会の十字架にはまだカンテラが灯っていなかった…

十分ほど待つとようやく点灯、やはりぽっと暖かくなる


★★★
朝、パラドールのテラスから地平線に朝日がゆっくりのぼってくるのが見える。


朝食の場所は太陽でいっぱいになる

おいしくて食べ過ぎてしまったら…中庭のあるロビーでゆっくりしましょう


- ガウディのバッリョ邸
-
エリア:
- ヨーロッパ>スペイン>バルセロナ
- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術
- 投稿日:2010/11/13 21:34
- コメント(0)
入場料ユーロ17.80は安くない。しかし、その価値を充分に感じさせてくれるバッリョ邸(日本の解説書の多くはバトリョ邸となっているが、現地の発音により近く表記いたします)。
入り口から二階への階段からすでに幻想的。

暖炉はまるできのこの様。

この建物が面するグラシア大通りは1877年ごろには建物が出来ていた。
バッリョ家は1900年に所有する事になり、1904年になってガウディに増改築を注文した。「はじめからガウディの設計になるものに比べて彼の個性が現れていないのでは?」いえいえ、むしろ人の器を使ったほうが個性が生きているように思われる。

この十字架と煙突の林立する空間は、ガウディの付け加えた五階部分の上にあたる。周辺の建物からアタマひとつ飛び出し、確実に違法建築なのだが、市に顔のきくバッリョ家が認可を出させたそうな。

お客が集まり人々が集う二階のサロン。道行く人々を眺め、また屋内の人も外から見られるショーケースである。

天井のこの渦巻きは巨大な目の様。

もう一階上の家族用居間の天井。

最上階は使用人たちが洗濯を干す為の乾燥室なのだが、ここにも圧倒的なガウディ的空間を見ることができる。

★光の井戸
地上階まで自然光を建物内に導く空間が貫かれている。

一見上部から下まで同じ色のタイルで装飾されているように感じさせるが、実は違う、近寄って見よう。

グラデーションのように見えるだろう。もっと近づいて見る。
上部の青色が濃く、下に行くほど白が多く使われているのがわかる。

これは、上部の方が自然光の白さを多く反射させて見えるのでより濃い色にしてあるという事。このグラデーションがあってはじめて、下から見上げた時に均質な青色が見上げられる※邸内の日本語音声ガイドによる。
その結果、なんだか水の中にいるような気分だということで、エレベーターのガラスもこんな水中の雰囲気になっているのだった。

日本語音声ガイドも充実していて、€17.80は見終わった後なら充分価値を感じさせてくれる場所であった。充分見学の時間を取れる時に訪問いたしましょう。
入り口から二階への階段からすでに幻想的。

暖炉はまるできのこの様。

この建物が面するグラシア大通りは1877年ごろには建物が出来ていた。
バッリョ家は1900年に所有する事になり、1904年になってガウディに増改築を注文した。「はじめからガウディの設計になるものに比べて彼の個性が現れていないのでは?」いえいえ、むしろ人の器を使ったほうが個性が生きているように思われる。

この十字架と煙突の林立する空間は、ガウディの付け加えた五階部分の上にあたる。周辺の建物からアタマひとつ飛び出し、確実に違法建築なのだが、市に顔のきくバッリョ家が認可を出させたそうな。

お客が集まり人々が集う二階のサロン。道行く人々を眺め、また屋内の人も外から見られるショーケースである。

天井のこの渦巻きは巨大な目の様。

もう一階上の家族用居間の天井。

最上階は使用人たちが洗濯を干す為の乾燥室なのだが、ここにも圧倒的なガウディ的空間を見ることができる。

★光の井戸
地上階まで自然光を建物内に導く空間が貫かれている。

一見上部から下まで同じ色のタイルで装飾されているように感じさせるが、実は違う、近寄って見よう。

グラデーションのように見えるだろう。もっと近づいて見る。
上部の青色が濃く、下に行くほど白が多く使われているのがわかる。

これは、上部の方が自然光の白さを多く反射させて見えるのでより濃い色にしてあるという事。このグラデーションがあってはじめて、下から見上げた時に均質な青色が見上げられる※邸内の日本語音声ガイドによる。
その結果、なんだか水の中にいるような気分だということで、エレベーターのガラスもこんな水中の雰囲気になっているのだった。

日本語音声ガイドも充実していて、€17.80は見終わった後なら充分価値を感じさせてくれる場所であった。充分見学の時間を取れる時に訪問いたしましょう。

- トレド大聖堂の天井に開けられた穴
-
エリア:
- ヨーロッパ>スペイン>トレド
- テーマ:街中・建物・景色 世界遺産 歴史・文化・芸術
- 投稿日:2010/11/12 03:04
- コメント(0)
スペインの教会中第一の地位を占めるトレド大聖堂。その天井には、建設後二百年を経て開けられたひとつの美しい穴がある。

大聖堂の屋根が完成したのは1493年とされている。まさにコロンブスの新大陸到達の翌年の事。この穴は1721年から32年の十年をかけて開けられた。
一度出来上がった大聖堂の屋根に穴を開けるのは非常に危険な事。ゴシックアーチのバランスを破壊すれば、屋根が落ちてきかねないのだ。そんな危険を侵してまでなぜこの穴を開けたのか?
真っ暗な教会中央の祭壇。心臓部にあるサンティッシモ・サクラメント礼拝堂に外部からの光を直接取り込みたいという我がままな希望。
ミサを行う時、「そこにあたかも神の様な光が射し込むのは感動的ではないか」とディエゴ・アストルガ大司教は思ったのだろう。
この難しい工事は、バジャドリド大学のファサードを装飾して評価を上げたナルシソ・トメという31歳の建築家に発注された。
バロック・ロココの派手な装飾だけでなく、建築的に難しい工事は十年の歳月をかけて完成。この作品「エル・トランスパレンテ」は、後世の我々にナルシソ・トメの代表作として記憶される事になったのである。

天井から落ちてきた光はこの複雑な装飾を通過して裏側の礼拝堂に届いているそうな。(我々は入る事ができませぬ)
彼以前にあったゴシック・ルネサンス風の壁に、バロックの「エル・トランスパルテ」が喰い込む如く接合されている。

我がままな、しかしなかなか効果的な大聖堂改造を注文した大司教ディエゴ・アストルガは、この「エル・トランスパルテ」のすぐ足元に葬られている。

大聖堂の屋根が完成したのは1493年とされている。まさにコロンブスの新大陸到達の翌年の事。この穴は1721年から32年の十年をかけて開けられた。
一度出来上がった大聖堂の屋根に穴を開けるのは非常に危険な事。ゴシックアーチのバランスを破壊すれば、屋根が落ちてきかねないのだ。そんな危険を侵してまでなぜこの穴を開けたのか?
真っ暗な教会中央の祭壇。心臓部にあるサンティッシモ・サクラメント礼拝堂に外部からの光を直接取り込みたいという我がままな希望。
ミサを行う時、「そこにあたかも神の様な光が射し込むのは感動的ではないか」とディエゴ・アストルガ大司教は思ったのだろう。
この難しい工事は、バジャドリド大学のファサードを装飾して評価を上げたナルシソ・トメという31歳の建築家に発注された。
バロック・ロココの派手な装飾だけでなく、建築的に難しい工事は十年の歳月をかけて完成。この作品「エル・トランスパレンテ」は、後世の我々にナルシソ・トメの代表作として記憶される事になったのである。

天井から落ちてきた光はこの複雑な装飾を通過して裏側の礼拝堂に届いているそうな。(我々は入る事ができませぬ)
彼以前にあったゴシック・ルネサンス風の壁に、バロックの「エル・トランスパルテ」が喰い込む如く接合されている。

我がままな、しかしなかなか効果的な大聖堂改造を注文した大司教ディエゴ・アストルガは、この「エル・トランスパルテ」のすぐ足元に葬られている。
1 - 5件目まで(6件中)



